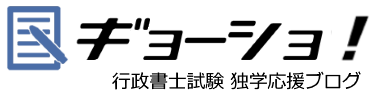行政書士試験の対策に判例学習は欠かせません。
多くの設問には「判例に照らし」の文言が入っていますし、判例を知らなければ解けない問題も少なくないからです。
そこで多くの受験生は主要な判例を収めた判例集を用意すると思います。
この記事では、判例集を使ってどのように判例を勉強していけば良いのかを考えます。
目次
判例集を使った判例学習の方法
本試験に至るまでの判例集の使い方を考えてみます。
判例集を読む前に、基本書で全体像をつかむ
判例が重要だとは言っても、判例だけを単体で勉強しても理解できないでしょう。
裁判は法令に基づいて行なわれます。
ですから、テキストを読んで条文をある程度理解してから判例集に進むのが良いでしょう。
ちなみに多くのテキスト・参考書には、主要判例が簡潔に載せられています。
しかし本試験では、判例の結果だけではなく、判例の要旨(判決に至る理由)まで理解している必要があります。
ですから判例学習は基本書だけではなく、判例集を使うのが良いでしょう。
判例集を1度通読してみる
基本書で試験範囲の全体像がつかめたら、判例集を一度通読してみましょう。
すべての重要判例に触れておくというのが趣旨なので、この段階で必死に覚える必要はありません。
判例集には、それがどんな事件についての判例なのかが簡単に説明されています。
退屈な勉強だと思わず、ショートショートを読むような感覚で読み進めるのがおすすめです。
「こんな事件があったんだ!」「えっ、こんな結末になっちゃうの?!」など、多くの発見や驚きがありますよ。
ノンフィクションなだけに、ある意味では小説よりも読み応えがあるかもしれません。
過去問・問題集に出てきた判例をチェックする
アウトプット段階に入ると、問題演習でさまざまな判例が出てくるでしょう。
間違えた問題を中心に、出題された判例を判例集でチェックしていくと、力が付くと思います。
その際、覚えておきたい重要な判例はテキスト(あるいはノート)に簡単に書き込んでおくとあとで役立ちます。
注意点として、問題集に出てくる判例がすべて重要とは限らないので、すべての判例を読み直す必要はないでしょう。
実力が付いてから再び通読する
本試験が近づいてきたら、もう一度判例集を通読しましょう。
理解が深まってから読むと、最初に通読したときとは違った発見がいろいろとあるはずです。
1つの判例にも複数の法令が関係しています。
たとえば憲法の判例を読むときには、民法や行政法との関連を考えながら読んでみましょう。
実際の試験でも、ある年には憲法で出題された判例が、別の年には民法で出題されることもあるのです。
「民法の判例は読まない」という戦略も
行政書士試験用の判例集には、試験科目すべての重要判例が収められています。
しかし私は、民法の判例は読まないことにしました。
おもな理由は、時間がなかったからです。
私が勉強を始めたときは本試験まで6か月を切っており、すべてをまんべんなく勉強することはできなかったのです。
もう1つの理由は、憲法や行政法と比べて、民法の場合は判例集を読む必要性を感じなかったからです。
もちろん民法においても判例学習は大切なのですが、テキストや参考書に触れられている範囲で対応できると思ったのです。
これには、憲法・行政法と民法の違いが関係しています。
憲法や行政法は「公法」といって国家と国民(または地方団体と住民)の関係を規律するもの。
法令は体系的にできており、具体的な事件(判例)とは切り離して考えやすいでしょう。
一方、民法は「私法」といって国民同士の関係を規律するものであるため、より複雑です。
国民同士のトラブルは千差万別なので、さまざまなケースを想定して法律が作られているわけです。
ですから、民法の条文を理解するには具体的な事件(判例)が必要であり、この2つを切り離して考えるのは難しいことです。
そのため、基本書で民法を勉強すると、判例知識も一緒に身に付くようになっているのです。
そのようなわけで私は民法については判例集の通読はしませんでした。
それでも本試験において民法はほぼ満点を取ることができました。(5肢択一:9問中8問、記述:満点)
ただし、この考え方は行政書士試験対策の王道というわけではありません。
十分に時間があるのであれば、民法についても判例集を読むに越したことはないでしょう。
(ちなみに私は商法・会社法に関しても、判例集は読みませんでした。
基本事項以外は手を出さない戦略を取ったからです。)
まとめ
判例集を使った学習は大切です。
- 基本知識を身に着けてから通読する
- 問題演習の際に個別の判例を読み直す
- 実力が付いてからもう一度通読する
このように、くり返し判例を読むことで合格レベルの力を身につけることができるでしょう。
民法の部分を読まないという戦略もありますが、時間が取れるのであればやっておくに越したことはありません。